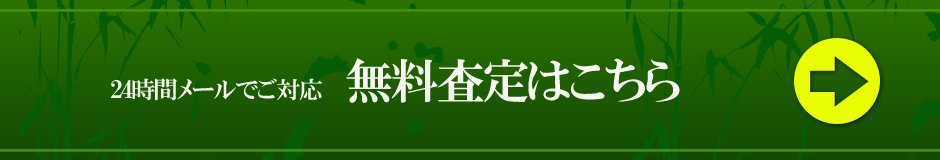丹波布の説明

丹波布とは、現在の兵庫県丹波市青垣である、丹波国佐治村で織られていた手紡ぎの絹と木綿とで交織にしている手織り布のことです。
その丹波布は佐治しまぬき、佐治木綿と言われ、丹波地方の佐治で、明治中頃まで盛んに織られていました。
木綿を栽培して、そこから糸をとり、植物染料の紫・茜・紅等の色は専門の染め屋で染め、白い絹を横糸にして、紬糸を織りこんで縞にしました。
木綿栽培をしているところではどこでも各種の植物染があって、自家用の衣料として、丹波布がおられていました。
丹波布は明治末期には一度すたれましたが、昭和二九年に復興するムードが高まり、当時の縞帳等に従って、製織が再び行われるようになりました。
丹波布の特徴ですが、緯糸に木綿のみならず、屑繭から紡いだ「つまみ糸」を織り込んでいることです。
藍と茶をベースとして、藍と茶と黄、藍と黄緑というような組み合わせで縞柄や格子柄を織り上げます。
染料は藍のほか、里山に自生する栗の皮、ヤマモモの樹皮、ハンノキの樹皮などを用いて、茶色を出し、田畑の畔道に生えるコブナグサ、キクイモ、ビワの樹皮をもちいて、黄色を出しています。すべては村の周辺で手に入る植物を使用してます。
これら自然の染料を媒染剤をいくつか使用したり、浸染の度合いを調整することで、微妙な色調を表現しています。